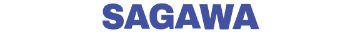時代のファッションリーダー
皇帝ナポレオン妃 ジョゼフィーヌ
ナポレオンはフランスの繊維産業としてのファッション産業の振興に熱心で『リヨンをヨーロッパの絹市場とするべし』と勅令を出した程です。 帝政が発足するとただちに宮廷サロンを復活させ、チュイルリ宮のサロンはマリー・アントワネットを凌ぐとさえゆわれる華やかなものでした。 当時の生地も薄く飾りも少なく、スタイルも停滞していた衣装の変化を求め、冬の寒さの中暖炉の火を落とさせたという話も有名です。 それでも寒さに震えながら薄いモスリンのドレスを着て、中には風邪をひいて亡くなったご夫人もいたとか。 女性の執念を感じますね。 1806年大陸封鎖例を発布してイギリスと国交を閉ざしますが、一つに産業革命で機械化したイギリスに対抗する為のものでもあったとか。 フランスの繊維業界を保護し機械化を進めるものという側面もありました。 実際この期間にルーヴェイとセダンの綿織物、サンタンクァンの麻とモスリン、バレンシアの白い麻の上布、レースなどの機械化が始められています。 そのナポレオンの初めの奥さんでしたジョゼフィーヌは戴冠式の絵で有名です。 一般的にナポレオンの奥さんというとほとんどのかたがマリア・ルイーズではなくジョゼフィーヌが浮かぶのではないでしょうか。 ルイ・イボリット・ルロア等によって創造されたエンパイアスタイルの女王ともいえるファッションリーダーでもありました。 さて、ジョゼフィーヌとはどういう人だったのでしょう。 祖父の代から母国を離れたクレオール(※1)の出身で、マルタレースで有名なフランス領西インド諸島マルティニーク島の生まれです。 結婚前の正式名は、マリー・ジョゼフ・ローズ・タシェ・ド・ラ・パジュリ(Marie Jos?phe Rose Tascher de la Pagerie)でした。 生家は貴族といっても名ばかりでエキゾチックな美貌の持ち主でしたが大変な浪費家でもありました。 1779年にアレクサンドル・ド・ボアルネ子爵と結婚し、一男ウジェーヌ・一女オルタンスをなします。 当初から夫婦仲が悪く、4年後の1783年に離婚しました。 離婚後にマルティニーク島の実家に戻っていたましたが島での暴動の多発に不安を感じてフランスに戻ります。 フランス革命のただ中で、元夫や友人の助命嘆願をしますが当局にこれを罪に問われてカルム監獄に投獄されてしまいます。 獄中では、ルイ=ラザール・オッシュ将軍の恋人となったという話もあります。 元夫のボアルネ子爵はギロチンで処刑されていますが、ジョゼフィーヌはロベスピエールが処刑されたことにより8月3日に釈放されました。 その後、総裁政府のポール・バラスの愛人となり、親友のテレーズ・カバリュス、ジュリエット・レカミエと並ぶ社交界の花形となって、「陽気な未亡人」と呼ばれました。 このころ、年下のナポレオンの求婚を受け1796年に結婚していますが、バラスが彼女に飽きてナポレオンに押しつけたという話もあります。 このときナポレオンは26歳、ジョゼフィーヌは32歳でしたが夫は2歳年上に、妻は4歳年下にさばをよみ、同い年の28歳として結婚証明書を提出しています。...
皇帝ナポレオン妃 ジョゼフィーヌ
ナポレオンはフランスの繊維産業としてのファッション産業の振興に熱心で『リヨンをヨーロッパの絹市場とするべし』と勅令を出した程です。 帝政が発足するとただちに宮廷サロンを復活させ、チュイルリ宮のサロンはマリー・アントワネットを凌ぐとさえゆわれる華やかなものでした。 当時の生地も薄く飾りも少なく、スタイルも停滞していた衣装の変化を求め、冬の寒さの中暖炉の火を落とさせたという話も有名です。 それでも寒さに震えながら薄いモスリンのドレスを着て、中には風邪をひいて亡くなったご夫人もいたとか。 女性の執念を感じますね。 1806年大陸封鎖例を発布してイギリスと国交を閉ざしますが、一つに産業革命で機械化したイギリスに対抗する為のものでもあったとか。 フランスの繊維業界を保護し機械化を進めるものという側面もありました。 実際この期間にルーヴェイとセダンの綿織物、サンタンクァンの麻とモスリン、バレンシアの白い麻の上布、レースなどの機械化が始められています。 そのナポレオンの初めの奥さんでしたジョゼフィーヌは戴冠式の絵で有名です。 一般的にナポレオンの奥さんというとほとんどのかたがマリア・ルイーズではなくジョゼフィーヌが浮かぶのではないでしょうか。 ルイ・イボリット・ルロア等によって創造されたエンパイアスタイルの女王ともいえるファッションリーダーでもありました。 さて、ジョゼフィーヌとはどういう人だったのでしょう。 祖父の代から母国を離れたクレオール(※1)の出身で、マルタレースで有名なフランス領西インド諸島マルティニーク島の生まれです。 結婚前の正式名は、マリー・ジョゼフ・ローズ・タシェ・ド・ラ・パジュリ(Marie Jos?phe Rose Tascher de la Pagerie)でした。 生家は貴族といっても名ばかりでエキゾチックな美貌の持ち主でしたが大変な浪費家でもありました。 1779年にアレクサンドル・ド・ボアルネ子爵と結婚し、一男ウジェーヌ・一女オルタンスをなします。 当初から夫婦仲が悪く、4年後の1783年に離婚しました。 離婚後にマルティニーク島の実家に戻っていたましたが島での暴動の多発に不安を感じてフランスに戻ります。 フランス革命のただ中で、元夫や友人の助命嘆願をしますが当局にこれを罪に問われてカルム監獄に投獄されてしまいます。 獄中では、ルイ=ラザール・オッシュ将軍の恋人となったという話もあります。 元夫のボアルネ子爵はギロチンで処刑されていますが、ジョゼフィーヌはロベスピエールが処刑されたことにより8月3日に釈放されました。 その後、総裁政府のポール・バラスの愛人となり、親友のテレーズ・カバリュス、ジュリエット・レカミエと並ぶ社交界の花形となって、「陽気な未亡人」と呼ばれました。 このころ、年下のナポレオンの求婚を受け1796年に結婚していますが、バラスが彼女に飽きてナポレオンに押しつけたという話もあります。 このときナポレオンは26歳、ジョゼフィーヌは32歳でしたが夫は2歳年上に、妻は4歳年下にさばをよみ、同い年の28歳として結婚証明書を提出しています。...
ルイ16世妃 マリー・アントワネット その4
その3より 民衆の怒りは貴族に向けられ、外国勢力と裏で結託していると思うようになります。 王党派とみられる貴族や新憲法に宣誓をしなかった司祭らに怒りの矛先が向けられ、彼らが幽閉されていた監獄が襲われマリー・アントワネットのよき理解者であったランバル公爵夫人もこのときに犠牲になっています。 公爵夫人の首は、槍の先に刺されてマリー・アントワネットの幽閉されたタンプル塔の窓に掲げられたなんてお話もあります。 裁判のための調査委員会により、テュイルリー宮殿のルイ16世の住居の別名『鉄の戸棚』からメモ魔だったルイ16世の様々な書類が発見され亡命者と連絡を取っていたこと、外国と交渉していたことなどがあきらかにされます。 12月11日、死刑に賛成が387票、反対が334票でしたが、賛成のうち執行猶予を望む票が26票あり、この表を反対票に加えると361対360となり、わずか1票の差で死刑が確定されたともいえます。 マリー・アントワネットは連打される太鼓と大砲の音で、夫の刑が執行されたことを知ります。 その絶望のなかで息子ルイ・シャルルの前に膝まづき、ルイ17世としての即位を讃えます。 窮地に立たされてはじめて自分がどういう立場の人間だったのかを自覚し、それにふさわしい態度で臨んだのでしょうね。 当時のフランスでは守衛にお金を払うと誰でもアントワネットと面会ができたそうで、いろんな面会人がやってきました。 ある日監視責任者のミショニが連れてきた面会人にアントワネットは見覚えがありました。 聖ルイ騎士団のルージュヴィルという人物で、民衆がテュイルリー宮殿に乱入したところを助けてくれた人でした。 彼はアントワネット救出の計画がありミショニもその1人であることなどを伝えます。 4日後の決行の夜、ミショニとルージュヴィルが独房に来てマリー・アントワネットをタンプル塔に移すことになったと牢番や監視兵に告げ、監視兵に付き添われ最後の扉を潜り抜け、まさに逃走用の馬車乗り込もうとしているそのときに監視兵がアントワネットを外に出すことに強く反対し、騒ぎとなり計画が失敗に終わりました。 この事件をきかっけに、それまでマリー・アントワネットに対する裁判に積極的ではなかった世間も一変して裁判への動きが強くなってしまいました。 革命政府の中にも外国との交渉の道具にマリー・アントワネットを使うという意見もあったのですが、肝心のオーストリアが交渉に乗ってくる気配がなく、仮に逃亡されたら反革命派の勢いがついて自分らの身が危ないと考えました。 マリー・アントワネットを裁判にかけることを強く望んだのがパリ市の幹部エベールと、革命裁判所検事総長のフーキエ・タンヴィルで、民衆もアントワネットの裁判を強く望んだために国民公会は裁判にかけることを決めました。 フーキエ・タンヴィルは革命裁判所の組織強化という名目で判事と陪審員を筋金入りの革命派で固めるました。 8歳の子供が証言するには詳細すぎて信憑性に欠けていますが、息子ルイ・シャルルは尋問の中で、マリー・アントワネットが何かしらの方法を使い外部の協力者と情報を交換していたこと、塔に派遣されたパリ市の役員に共犯者がいるのではないかという嫌疑を全部認めたとされています。 しかし、エリザベートとテレーズの証言の一問一答が記録されているにもかかわらず、シャルルの証言は、あとからまとめて書かれたものでした。 どんな手を使ってでもマリー・アントワネットを有罪にしたかったのです。 フランス革命の背景となったものにルイ14世の晩年頃から既に陰りを見せていた国家財政が、ルイ15世時代のポーランド継承戦争・オーストリア継承戦争・七年戦争などで更に逼迫していました。 ルイ16世はこれをなんと建て直すべく、はじめテュルゴー(A.R.Jacque Turgot)を財務総監にして国政改革に力を入れ、それが貴族・ 僧侶の抵抗で1776年辞任に追い込まれると、今度はネッケル(Jacque Necker)を財務長官にして、改革路線を更に推進します。 しかし彼に対しても貴族・僧侶の抵抗は強く1781年、彼も辞任に追い込まれてルイ16世は苦境に立たされます。 民衆側はなかなか進まない改革に不満が蓄積していて、このネッケル解任は王制への不信と制御の効かない怒りへと押し進めていきました。 また、ルイ15世の時代には気候もよく、農作物が豊富に獲れて人々は比較的豊かな生活をおくっていました。 ルイ16世の時代になると天候は悪く、農作物も不作で、唯一豊作だったブドウのお陰でワインの価格は逆に値崩れを起こし、人々の暮らしはとても苦しいものになっていました。...
ルイ16世妃 マリー・アントワネット その4
その3より 民衆の怒りは貴族に向けられ、外国勢力と裏で結託していると思うようになります。 王党派とみられる貴族や新憲法に宣誓をしなかった司祭らに怒りの矛先が向けられ、彼らが幽閉されていた監獄が襲われマリー・アントワネットのよき理解者であったランバル公爵夫人もこのときに犠牲になっています。 公爵夫人の首は、槍の先に刺されてマリー・アントワネットの幽閉されたタンプル塔の窓に掲げられたなんてお話もあります。 裁判のための調査委員会により、テュイルリー宮殿のルイ16世の住居の別名『鉄の戸棚』からメモ魔だったルイ16世の様々な書類が発見され亡命者と連絡を取っていたこと、外国と交渉していたことなどがあきらかにされます。 12月11日、死刑に賛成が387票、反対が334票でしたが、賛成のうち執行猶予を望む票が26票あり、この表を反対票に加えると361対360となり、わずか1票の差で死刑が確定されたともいえます。 マリー・アントワネットは連打される太鼓と大砲の音で、夫の刑が執行されたことを知ります。 その絶望のなかで息子ルイ・シャルルの前に膝まづき、ルイ17世としての即位を讃えます。 窮地に立たされてはじめて自分がどういう立場の人間だったのかを自覚し、それにふさわしい態度で臨んだのでしょうね。 当時のフランスでは守衛にお金を払うと誰でもアントワネットと面会ができたそうで、いろんな面会人がやってきました。 ある日監視責任者のミショニが連れてきた面会人にアントワネットは見覚えがありました。 聖ルイ騎士団のルージュヴィルという人物で、民衆がテュイルリー宮殿に乱入したところを助けてくれた人でした。 彼はアントワネット救出の計画がありミショニもその1人であることなどを伝えます。 4日後の決行の夜、ミショニとルージュヴィルが独房に来てマリー・アントワネットをタンプル塔に移すことになったと牢番や監視兵に告げ、監視兵に付き添われ最後の扉を潜り抜け、まさに逃走用の馬車乗り込もうとしているそのときに監視兵がアントワネットを外に出すことに強く反対し、騒ぎとなり計画が失敗に終わりました。 この事件をきかっけに、それまでマリー・アントワネットに対する裁判に積極的ではなかった世間も一変して裁判への動きが強くなってしまいました。 革命政府の中にも外国との交渉の道具にマリー・アントワネットを使うという意見もあったのですが、肝心のオーストリアが交渉に乗ってくる気配がなく、仮に逃亡されたら反革命派の勢いがついて自分らの身が危ないと考えました。 マリー・アントワネットを裁判にかけることを強く望んだのがパリ市の幹部エベールと、革命裁判所検事総長のフーキエ・タンヴィルで、民衆もアントワネットの裁判を強く望んだために国民公会は裁判にかけることを決めました。 フーキエ・タンヴィルは革命裁判所の組織強化という名目で判事と陪審員を筋金入りの革命派で固めるました。 8歳の子供が証言するには詳細すぎて信憑性に欠けていますが、息子ルイ・シャルルは尋問の中で、マリー・アントワネットが何かしらの方法を使い外部の協力者と情報を交換していたこと、塔に派遣されたパリ市の役員に共犯者がいるのではないかという嫌疑を全部認めたとされています。 しかし、エリザベートとテレーズの証言の一問一答が記録されているにもかかわらず、シャルルの証言は、あとからまとめて書かれたものでした。 どんな手を使ってでもマリー・アントワネットを有罪にしたかったのです。 フランス革命の背景となったものにルイ14世の晩年頃から既に陰りを見せていた国家財政が、ルイ15世時代のポーランド継承戦争・オーストリア継承戦争・七年戦争などで更に逼迫していました。 ルイ16世はこれをなんと建て直すべく、はじめテュルゴー(A.R.Jacque Turgot)を財務総監にして国政改革に力を入れ、それが貴族・ 僧侶の抵抗で1776年辞任に追い込まれると、今度はネッケル(Jacque Necker)を財務長官にして、改革路線を更に推進します。 しかし彼に対しても貴族・僧侶の抵抗は強く1781年、彼も辞任に追い込まれてルイ16世は苦境に立たされます。 民衆側はなかなか進まない改革に不満が蓄積していて、このネッケル解任は王制への不信と制御の効かない怒りへと押し進めていきました。 また、ルイ15世の時代には気候もよく、農作物が豊富に獲れて人々は比較的豊かな生活をおくっていました。 ルイ16世の時代になると天候は悪く、農作物も不作で、唯一豊作だったブドウのお陰でワインの価格は逆に値崩れを起こし、人々の暮らしはとても苦しいものになっていました。...
ルイ16世妃マリー・アントワネット その3 王制の黄昏
その2より 人々にとってこの事件は王妃を中傷するネタに過ぎず、この首飾り事件はフランス王政が揺らぐ大きなきっかけともなりました。 1789年7月14日、フランスでは王政に対する民衆の不満が爆発し、フランス革命が勃発しました。 ポリニャック伯夫人ら親しくしていた貴族たちも彼女を見捨てて亡命してしまいます。 彼女に最後まで残ったのは、王妹エリザベートとランバル公妃マリー・ルイーズだけでした。 国王一家は身柄をヴェルサイユ宮殿から、パリのテュイルリー宮殿に身柄を移されることになります。 民衆の望みは国王一家がパリで一緒に暮らし、自分達と共存していくことでした。 ですからパリに身柄を移された国王一家を歓迎している面もあったのです。 この城を使用するのは150年ぶりで、あちこち大幅に手を入れる必要がありました。 ヴェルサイユ宮殿からは家具が運ばれ、家族水いらずの生活を送ることになります。 ルイ16世もマリー・アントワネットも、舞踏会や観劇、音楽会を自粛して、自らが捕虜のように振る舞い、滅多に外出することはありませんでした。 しかし、このような国王夫婦の萎縮した態度は民衆から逆に王という存在への畏怖の念を取り払うものとなりました。 憲法制定の準備を議会が進める中、決定的な影響力を持っていたのが立憲王政を支持していたミラボー伯爵でした。 ミラボーはルイ16世に革命を受け入れさせた上で手を結ぼうと考えていました。 フェルセン伯爵はマリー・アントワネットと愛し合っていて、私財を投じて国王一家の逃亡に力を貸そうと決意し、アントワネットの兄レオポルト2世に助けを求めフランスから脱出しようと計画しました。 ミラボーもパリから脱出すること自体に反対ではありませんでした。 しかしフェルセンと違うところは外国の軍隊を頼りに逃亡するのではなく、フランス軍を頼りに昼間堂々と行うべきだとしたものでしたがこの考えは聞き入れられなかったのでした。 庶民に化けたつもりの国王と王妃は、それぞれ別の馬車に乗ることを勧められますが王妃は家族全員が乗ることのできる大きな馬車に、銀の食器や衣裳箪笥、食料品や酒蔵一つ分のワイン樽を積んで出発してしまいます。 荷物を満載した速度のでないこの馬大きな車は、ほどなく捕えられます。 このヴァレンヌ事件をきっかけに、国王一家は親国王派の国民からも見離されてしまいます。 ヴァレンヌ事件によってタンプル塔に幽閉されることになったルイ16世一家がパリに連れ戻される前にシャロンに到着すると、このシャロン近くの領主ダンピエル伯がルイ16世らの乗った馬車に近づき表敬の挨拶をしたところ、これを観て怒った民衆に惨殺されてしまいます。 どれだけ一触即発の空気が流れていたのかが分かります。 パリ移送にはもう一つ話があります。 戻るまでの道すがら、途中から議会から派遣されてきた国王一家を連行する委員3名が一緒に馬車に乗ります。 この3人はこの馬車の中でマリー・アントワネットが想像していたようなとんでもない女性ではなく、人の話しに真摯に耳を傾ける魅力的な女性であること、王が自ら王子の放尿を手伝っていたこと、王族も個人で見ると自分達となんら変わらないことを知り、すっかり王党派寄りの考えを持ってしまい、後の議会では王の免責を主張するまでになったそうです。 そんな中、フランスはオーストリアに宣戦布告し、それを知ったアントワネットはフランスの情報をオーストリアに通報し続けます。 アントワネットにとってこれは裏切りのつもりではなく、フランスが負けることより連合軍によって王家が開放されることを望んでいたからでした。 アントワネットにとってフランスとは王家だった訳です。 フランスで議会が『祖国の危機』を宣言し、オ?ストリア連合軍の総司令官ブラウンシュヴァイク公爵が出した『国王に従うこと』『テュイルリー宮殿を襲撃したらパリを全滅させる』とした宣言は意図とは逆に民衆の怒りの炎に油を注ぐことになりました。 民衆にとっては戦争の相手国が自分らの王様と手を結んでいると宣言されたのですから。...
ルイ16世妃マリー・アントワネット その3 王制の黄昏
その2より 人々にとってこの事件は王妃を中傷するネタに過ぎず、この首飾り事件はフランス王政が揺らぐ大きなきっかけともなりました。 1789年7月14日、フランスでは王政に対する民衆の不満が爆発し、フランス革命が勃発しました。 ポリニャック伯夫人ら親しくしていた貴族たちも彼女を見捨てて亡命してしまいます。 彼女に最後まで残ったのは、王妹エリザベートとランバル公妃マリー・ルイーズだけでした。 国王一家は身柄をヴェルサイユ宮殿から、パリのテュイルリー宮殿に身柄を移されることになります。 民衆の望みは国王一家がパリで一緒に暮らし、自分達と共存していくことでした。 ですからパリに身柄を移された国王一家を歓迎している面もあったのです。 この城を使用するのは150年ぶりで、あちこち大幅に手を入れる必要がありました。 ヴェルサイユ宮殿からは家具が運ばれ、家族水いらずの生活を送ることになります。 ルイ16世もマリー・アントワネットも、舞踏会や観劇、音楽会を自粛して、自らが捕虜のように振る舞い、滅多に外出することはありませんでした。 しかし、このような国王夫婦の萎縮した態度は民衆から逆に王という存在への畏怖の念を取り払うものとなりました。 憲法制定の準備を議会が進める中、決定的な影響力を持っていたのが立憲王政を支持していたミラボー伯爵でした。 ミラボーはルイ16世に革命を受け入れさせた上で手を結ぼうと考えていました。 フェルセン伯爵はマリー・アントワネットと愛し合っていて、私財を投じて国王一家の逃亡に力を貸そうと決意し、アントワネットの兄レオポルト2世に助けを求めフランスから脱出しようと計画しました。 ミラボーもパリから脱出すること自体に反対ではありませんでした。 しかしフェルセンと違うところは外国の軍隊を頼りに逃亡するのではなく、フランス軍を頼りに昼間堂々と行うべきだとしたものでしたがこの考えは聞き入れられなかったのでした。 庶民に化けたつもりの国王と王妃は、それぞれ別の馬車に乗ることを勧められますが王妃は家族全員が乗ることのできる大きな馬車に、銀の食器や衣裳箪笥、食料品や酒蔵一つ分のワイン樽を積んで出発してしまいます。 荷物を満載した速度のでないこの馬大きな車は、ほどなく捕えられます。 このヴァレンヌ事件をきっかけに、国王一家は親国王派の国民からも見離されてしまいます。 ヴァレンヌ事件によってタンプル塔に幽閉されることになったルイ16世一家がパリに連れ戻される前にシャロンに到着すると、このシャロン近くの領主ダンピエル伯がルイ16世らの乗った馬車に近づき表敬の挨拶をしたところ、これを観て怒った民衆に惨殺されてしまいます。 どれだけ一触即発の空気が流れていたのかが分かります。 パリ移送にはもう一つ話があります。 戻るまでの道すがら、途中から議会から派遣されてきた国王一家を連行する委員3名が一緒に馬車に乗ります。 この3人はこの馬車の中でマリー・アントワネットが想像していたようなとんでもない女性ではなく、人の話しに真摯に耳を傾ける魅力的な女性であること、王が自ら王子の放尿を手伝っていたこと、王族も個人で見ると自分達となんら変わらないことを知り、すっかり王党派寄りの考えを持ってしまい、後の議会では王の免責を主張するまでになったそうです。 そんな中、フランスはオーストリアに宣戦布告し、それを知ったアントワネットはフランスの情報をオーストリアに通報し続けます。 アントワネットにとってこれは裏切りのつもりではなく、フランスが負けることより連合軍によって王家が開放されることを望んでいたからでした。 アントワネットにとってフランスとは王家だった訳です。 フランスで議会が『祖国の危機』を宣言し、オ?ストリア連合軍の総司令官ブラウンシュヴァイク公爵が出した『国王に従うこと』『テュイルリー宮殿を襲撃したらパリを全滅させる』とした宣言は意図とは逆に民衆の怒りの炎に油を注ぐことになりました。 民衆にとっては戦争の相手国が自分らの王様と手を結んでいると宣言されたのですから。...
ルイ16世妃マリー・アントワネット その2 首飾り事件
その1より 復刻された首飾り 宮廷御用達宝石商として、マリー・アントワネットに宝石を売っていた宝石工・バッサンジュとベーマーという男がいました。 ベーマーはルイ15世の寵姫デュ・バリー夫人が買ってくれることを当てにして、1774年頃、豪華な首飾りの製作を始めていました。 ベーマーが八方手を尽くして探し求めたダイヤが540粒も使われていて、それをバッサンジュが丹念に研磨して細工を施したものです。 しかし、デュ・バリー夫人はルイ15世が亡くなったために没落してしまいます。 ほぼ完成していて、現在の金額で数十億円という首飾りを買えるのは、マリー・アントワネットしかいないと考えます。 1785年2月、この首飾りを作るために莫大な借金をしていたバーマーのもとにロアン枢機卿(※1)から王妃が首飾りを購入してくれるとの朗報が届きます。 屋敷を訪れたベーマーとバッサンジュにロアンは王妃が首飾りを買い上げるとする書類を見せました。 王妃が署名するときは、洗礼名しか書かないことは誰もが知ることだったのですが『マリー・アントワネット・ド・フランス』と署名されていました。 首飾りの支払いは4回に分けて支払われることになり、ベーマーとバッサンジュは首飾りをロアン枢機卿に手渡します。 1回目の支払い日に、ベーマーがアントワネット妃側近のカンパン夫人に首飾りの代金を請求すると、『王妃は首飾りを受け取ってはいません。』という返事が返ってきます。 ロアン枢機卿という人物はなんとかマリー・アントワネットに取り入ろうとしていましたが、かつてウィーンの宮廷でマリア・テレジアの不興を買ってしまい、アントワネットにも嫌われていた人物でした。 マリー・アントワネットは激怒して、「自分が嫌っているロアン枢機卿から宝石など買うわけがない、事件の首謀者はロアンで自分の名前をかたって宝石を騙し取ったに違いない』とルイ16世に訴え、ロアンは宮廷の鏡の間で逮捕され裁判にかけられることになりました。 事件の中心人物が、王妃と枢機卿とという大スキャンダルにフランス中が沸きあがります。 そしてここでもアントワネットは賄賂として首飾りを枢機卿に贈らせたとか、宝石を売りさばいたお金をオーストリアに送っていたといった世間の悪意のある風評の的にされます。 ロアン枢機卿の一族は独自に調査を行い、自称ラ・モット伯爵婦人(※2)が首謀者であるということをつきとめ関係者が逮捕されました。 宝石商が王妃に首飾りを売りたがっているのを知ったラ・モット伯爵夫人は、自分の身分をもっと出世させたいと企み、ロアン枢機卿に王妃の欲しがっている首飾りを献上すれば会ってもらえると話を持ちかけます。 更には、王妃を語った偽の手紙を渡します。 『これまでのことは水に流しましょう』とする内容のもので、偽の手紙は200通以上2人の間で交わされたともいわれています。 ロアンは手紙だけでは物足りなくなり、直接王妃と会いたいと言い出します。 そこでラ・モット伯爵夫人は、マリー・アントワネットによく似た娼婦を用意し、月明かりの木陰の下で殆ど言葉も交わさない接見を果たしました。 ラ・モット婦人とはあの手この手の確信犯だったのです。 ロアン枢機卿はルイ16世に事後承認させることにし、(充分越権行為ですし、結果に責任があると思うのですが・・。)ラ・モット伯爵夫人の用意した偽の首飾りを購入する旨の書類を用意し、ロアンから宝石商へと書類が渡り、首飾りは宝石商からロアンへ、ロアンからラ・モット伯爵夫人へと渡りました。。 そして首飾りはラ・モット伯爵夫人によりバラバラにされてフランスやイギリス各地に売りさばかれてしまいます。 今に残されていれば歴史的文化遺産となりえたのにもったいないですね。 裁判の結果、ロアンは無罪となります。 民衆からは『万歳』の声があがるなかマリー・アントワネットは悔しさで泣き崩れたそうです。 この判決にも背景があり、パリ高等法院は政治的に宮廷と対立していたので王妃にとって都合の悪い判決を下したのでした。...
ルイ16世妃マリー・アントワネット その2 首飾り事件
その1より 復刻された首飾り 宮廷御用達宝石商として、マリー・アントワネットに宝石を売っていた宝石工・バッサンジュとベーマーという男がいました。 ベーマーはルイ15世の寵姫デュ・バリー夫人が買ってくれることを当てにして、1774年頃、豪華な首飾りの製作を始めていました。 ベーマーが八方手を尽くして探し求めたダイヤが540粒も使われていて、それをバッサンジュが丹念に研磨して細工を施したものです。 しかし、デュ・バリー夫人はルイ15世が亡くなったために没落してしまいます。 ほぼ完成していて、現在の金額で数十億円という首飾りを買えるのは、マリー・アントワネットしかいないと考えます。 1785年2月、この首飾りを作るために莫大な借金をしていたバーマーのもとにロアン枢機卿(※1)から王妃が首飾りを購入してくれるとの朗報が届きます。 屋敷を訪れたベーマーとバッサンジュにロアンは王妃が首飾りを買い上げるとする書類を見せました。 王妃が署名するときは、洗礼名しか書かないことは誰もが知ることだったのですが『マリー・アントワネット・ド・フランス』と署名されていました。 首飾りの支払いは4回に分けて支払われることになり、ベーマーとバッサンジュは首飾りをロアン枢機卿に手渡します。 1回目の支払い日に、ベーマーがアントワネット妃側近のカンパン夫人に首飾りの代金を請求すると、『王妃は首飾りを受け取ってはいません。』という返事が返ってきます。 ロアン枢機卿という人物はなんとかマリー・アントワネットに取り入ろうとしていましたが、かつてウィーンの宮廷でマリア・テレジアの不興を買ってしまい、アントワネットにも嫌われていた人物でした。 マリー・アントワネットは激怒して、「自分が嫌っているロアン枢機卿から宝石など買うわけがない、事件の首謀者はロアンで自分の名前をかたって宝石を騙し取ったに違いない』とルイ16世に訴え、ロアンは宮廷の鏡の間で逮捕され裁判にかけられることになりました。 事件の中心人物が、王妃と枢機卿とという大スキャンダルにフランス中が沸きあがります。 そしてここでもアントワネットは賄賂として首飾りを枢機卿に贈らせたとか、宝石を売りさばいたお金をオーストリアに送っていたといった世間の悪意のある風評の的にされます。 ロアン枢機卿の一族は独自に調査を行い、自称ラ・モット伯爵婦人(※2)が首謀者であるということをつきとめ関係者が逮捕されました。 宝石商が王妃に首飾りを売りたがっているのを知ったラ・モット伯爵夫人は、自分の身分をもっと出世させたいと企み、ロアン枢機卿に王妃の欲しがっている首飾りを献上すれば会ってもらえると話を持ちかけます。 更には、王妃を語った偽の手紙を渡します。 『これまでのことは水に流しましょう』とする内容のもので、偽の手紙は200通以上2人の間で交わされたともいわれています。 ロアンは手紙だけでは物足りなくなり、直接王妃と会いたいと言い出します。 そこでラ・モット伯爵夫人は、マリー・アントワネットによく似た娼婦を用意し、月明かりの木陰の下で殆ど言葉も交わさない接見を果たしました。 ラ・モット婦人とはあの手この手の確信犯だったのです。 ロアン枢機卿はルイ16世に事後承認させることにし、(充分越権行為ですし、結果に責任があると思うのですが・・。)ラ・モット伯爵夫人の用意した偽の首飾りを購入する旨の書類を用意し、ロアンから宝石商へと書類が渡り、首飾りは宝石商からロアンへ、ロアンからラ・モット伯爵夫人へと渡りました。。 そして首飾りはラ・モット伯爵夫人によりバラバラにされてフランスやイギリス各地に売りさばかれてしまいます。 今に残されていれば歴史的文化遺産となりえたのにもったいないですね。 裁判の結果、ロアンは無罪となります。 民衆からは『万歳』の声があがるなかマリー・アントワネットは悔しさで泣き崩れたそうです。 この判決にも背景があり、パリ高等法院は政治的に宮廷と対立していたので王妃にとって都合の悪い判決を下したのでした。...
ルイ16世妃 マリー・アントワネット その1
ロココのファッションリーダーの一人、ルイ16世妃マリー・アントワネットは国家を傾かせる程の散在をした悪女として市民に処刑されてしまいましたが、果たしてどんな女性だったのでしょう。 マリー・アントワネットは女帝マリア・テレジア(※1)と神聖ローマ皇帝フランツ1世の皇女で、マリア・アントニアという名前でした。 マリア・テレジアは女帝と呼ばれた女性でしたが、私生活では良き妻であり、良き母親でした。 他の王室と違いとても家庭的な環境ですくすくと育ち、4歳で社交界デビューしています。 10歳のとき父である神聖ローマ帝国皇帝フランツ1世が亡くなり大きく運命が動き始めます。 当時プロイセンのフリードリヒ2世(※2)に国土を脅かされていたマリア・テレジアは、ロシアの女帝エリザヴェータとルイ15世の愛妾ポンパドゥール夫人の協力を得てプロイセンに対抗する勢力を作り上げました。 そうしてオーストリア・ハプスブルク家とフランス・ブルボン家とは長年ヨーロッパの覇権を巡って激しい対立をしてきましたが、1756年にフランス王ルイ15世と同盟を結ぶことに成功します。 俗に “ 3枚のペチコート作戦 ” ※3といわれるものです。 長年の宿敵フランスとより強い結びつきを確保するために王太子ルイとマリア・テレジアの末娘マリー・アントワネットの縁談がとりまとめられました。 ルイ(後の16世)はルイ15世の孫にあたりますが、父のルイが早世したため王太子になりました。 そして1770年、14歳になったマリー・アントワネットと16歳のルイは国民の祝福を受けながら華々しく結婚しました。 1774年5月10日、フランス王ルイ15世がこの世を去り、ルイ・オーギュストがフランス王ルイ16世となり、マリー・アントワネットも18歳で王妃となります。 当初マリー・アントワネットは宮廷の娯楽に関する一切を任されたために毎週3回の芝居、2回の舞踏会を催していました。 パリの街がお気に入りで、お忍びで仮面舞踏会に出かけては素性を隠して誰彼かまわずお喋りしたり踊ったりしていました。 これらの軽率な行動を母マリア・テレジアにも手紙でたしなめられましたが、アントワネットの行動にストップはかかりませんでした。 オーストリアの自由で家庭的な宮廷で育ったアントワネットにとって、堅苦しいヴェルサイユ宮殿での暮らしが退屈で息が詰まりそうで、その反動だったかもしれませんね。 朝の接見を簡素化させたり、全王族の食事風景を公開することや(王と王妃の夜伽の公開まであったとか)、王妃に直接物を渡してはならないなどのベルサイユの習慣や儀式を自分の意に添わない人物は宮廷から追い出してしまうなどのやりかたで廃止・緩和させました。 しかし、誰が王妃に下着を渡すかでもめたり、地位によって便器の形が違ったりすることが一種のステイタスを奪われた宮廷内の人々にとっては、アントワネットが彼らの特権を奪う形になってしまい、彼ら自身も無駄とは思っていたでしょうが逆に反感を買ってしまうこととなります。 ヴェルサイユ宮殿から1キロほど離れたところにアントワネットが作らせた離宮プチ・トリアノンは、唯一のんびり過ごすことができた場所でした。 ここでの権限はマリー・アントワネットにあり、ルイ16世ですら客人として扱われる場所だったのです。 プチ・トリアノンの工事が行われているときアントワネットはたびたび総務監督と揉め事を起こしています。 人々は王妃の莫大な出費に対して不満を口にするようになってゆきました。 ヴェルサイユ宮殿とその庭園は全て民衆に解放されている場所でしたが、プチ・トリアノンはマリー・アントワネットの特別な許可がなければ足を踏み入れることのできない、それゆえ人々の好奇心を大きくし悪い噂を生む場所ともなっていきます。 この離宮に招かれた者は誰もが気ままに過ごし、アントワネットが居間に入ってきても誰も会話を止めず、刺繍の手も休めず、楽器の演奏を止めることもなく、アントワネットも皆の中に加わって会話に花を咲かせるような内輪のきさくな空間だったのですが、公開されたヴェルサイユ宮殿と違ったプチ・トリアノンで何が行われているのか、庶民の妄想をかき立てる材料となったのです。 ところがアントワネットは自由気ままに過ごせるプチ・トリアノンでも物足りないものを感じるようになっていきました。 そこで離宮の庭園に大きな池を掘り、池のほとりには塔や納屋、はと小屋やニワトリ小屋、風車小屋などを作り、更には番人小屋や小さなわらぶき屋根の家まで建て、住み込みで働く農夫婦、庭師、牛飼いなどもいる人工的な田舎、アモーが作られました。...
ルイ16世妃 マリー・アントワネット その1
ロココのファッションリーダーの一人、ルイ16世妃マリー・アントワネットは国家を傾かせる程の散在をした悪女として市民に処刑されてしまいましたが、果たしてどんな女性だったのでしょう。 マリー・アントワネットは女帝マリア・テレジア(※1)と神聖ローマ皇帝フランツ1世の皇女で、マリア・アントニアという名前でした。 マリア・テレジアは女帝と呼ばれた女性でしたが、私生活では良き妻であり、良き母親でした。 他の王室と違いとても家庭的な環境ですくすくと育ち、4歳で社交界デビューしています。 10歳のとき父である神聖ローマ帝国皇帝フランツ1世が亡くなり大きく運命が動き始めます。 当時プロイセンのフリードリヒ2世(※2)に国土を脅かされていたマリア・テレジアは、ロシアの女帝エリザヴェータとルイ15世の愛妾ポンパドゥール夫人の協力を得てプロイセンに対抗する勢力を作り上げました。 そうしてオーストリア・ハプスブルク家とフランス・ブルボン家とは長年ヨーロッパの覇権を巡って激しい対立をしてきましたが、1756年にフランス王ルイ15世と同盟を結ぶことに成功します。 俗に “ 3枚のペチコート作戦 ” ※3といわれるものです。 長年の宿敵フランスとより強い結びつきを確保するために王太子ルイとマリア・テレジアの末娘マリー・アントワネットの縁談がとりまとめられました。 ルイ(後の16世)はルイ15世の孫にあたりますが、父のルイが早世したため王太子になりました。 そして1770年、14歳になったマリー・アントワネットと16歳のルイは国民の祝福を受けながら華々しく結婚しました。 1774年5月10日、フランス王ルイ15世がこの世を去り、ルイ・オーギュストがフランス王ルイ16世となり、マリー・アントワネットも18歳で王妃となります。 当初マリー・アントワネットは宮廷の娯楽に関する一切を任されたために毎週3回の芝居、2回の舞踏会を催していました。 パリの街がお気に入りで、お忍びで仮面舞踏会に出かけては素性を隠して誰彼かまわずお喋りしたり踊ったりしていました。 これらの軽率な行動を母マリア・テレジアにも手紙でたしなめられましたが、アントワネットの行動にストップはかかりませんでした。 オーストリアの自由で家庭的な宮廷で育ったアントワネットにとって、堅苦しいヴェルサイユ宮殿での暮らしが退屈で息が詰まりそうで、その反動だったかもしれませんね。 朝の接見を簡素化させたり、全王族の食事風景を公開することや(王と王妃の夜伽の公開まであったとか)、王妃に直接物を渡してはならないなどのベルサイユの習慣や儀式を自分の意に添わない人物は宮廷から追い出してしまうなどのやりかたで廃止・緩和させました。 しかし、誰が王妃に下着を渡すかでもめたり、地位によって便器の形が違ったりすることが一種のステイタスを奪われた宮廷内の人々にとっては、アントワネットが彼らの特権を奪う形になってしまい、彼ら自身も無駄とは思っていたでしょうが逆に反感を買ってしまうこととなります。 ヴェルサイユ宮殿から1キロほど離れたところにアントワネットが作らせた離宮プチ・トリアノンは、唯一のんびり過ごすことができた場所でした。 ここでの権限はマリー・アントワネットにあり、ルイ16世ですら客人として扱われる場所だったのです。 プチ・トリアノンの工事が行われているときアントワネットはたびたび総務監督と揉め事を起こしています。 人々は王妃の莫大な出費に対して不満を口にするようになってゆきました。 ヴェルサイユ宮殿とその庭園は全て民衆に解放されている場所でしたが、プチ・トリアノンはマリー・アントワネットの特別な許可がなければ足を踏み入れることのできない、それゆえ人々の好奇心を大きくし悪い噂を生む場所ともなっていきます。 この離宮に招かれた者は誰もが気ままに過ごし、アントワネットが居間に入ってきても誰も会話を止めず、刺繍の手も休めず、楽器の演奏を止めることもなく、アントワネットも皆の中に加わって会話に花を咲かせるような内輪のきさくな空間だったのですが、公開されたヴェルサイユ宮殿と違ったプチ・トリアノンで何が行われているのか、庶民の妄想をかき立てる材料となったのです。 ところがアントワネットは自由気ままに過ごせるプチ・トリアノンでも物足りないものを感じるようになっていきました。 そこで離宮の庭園に大きな池を掘り、池のほとりには塔や納屋、はと小屋やニワトリ小屋、風車小屋などを作り、更には番人小屋や小さなわらぶき屋根の家まで建て、住み込みで働く農夫婦、庭師、牛飼いなどもいる人工的な田舎、アモーが作られました。...
ロココの女王 マリー・アントワネット
アントワネットは湯水のごとくドレスに国費を使って国を傾けたといわれていますが、本当はどうだったのでしょう。 半世紀前の1725年から王妃の衣装代は年間12万ルーブルと予算が組まれていました。 シーズンごとに正装用、礼装用、ドレスを各3枚、年間にすると各12枚が新調される約束で、最低でも36着は規則によって与えられます。 これとは別に王妃にはお手元金という300〜400ルーヴルのポケットマネーの予算もありました。 しかし、実際の王妃のお買い物は年間170着のドレス、25万ルーブルの腕輪や50万ルーブルの耳飾りなども求めています。 日本からも漆器の化粧道具箱や宝石箱などを注文して作らせています。 2年程前にそれらのアントワネットコレクションの数々を京都の国立博物館で観てまいりました。 他の海外の漆器のコレクションに比べ、女性的なセンスの良さには驚かされました。 展示内容に若干の違いがありますが、東京ではサントリー美術館でも展示がされたのでご覧になられたかとも多いと思います。 さて、大きく予算を超えていますが王室の費やす金額は果たして財政を破綻させるほどのものなのでしょうか。 王室の費用というのは国庫の10%に満たない額です。 国庫の10%、大きいですがそれだけでは国が破綻するとは思えません。 マリア・テレジアはマリー・アントワネットへファッションへの逃避を慎むように手紙を送っていました。 マリー・アントワネットはローズ・ベルタンに「パンドラ」という木と陶器のお人形をつくらせます。 そしてそれにベルタンのつくる最新のモードのドレスを着せ、絹の靴下からアクセサリー、宝石、最新のヘアースタイルのカツラ、帽子や孔雀の羽などの全てを身につけさせ母マリア・テレジアと姉妹たちへの贈ります。 これが非常に人気をよび、等身大に近いものがつくられるようになります。 これを各国王室・宮廷に送り、さらなる流行を作りだし、注文を受けたのでした。 フランスの殖産産業としてのファッション戦略はすでにありましたが、これほど明確なものはかつて無かったように思います。 ロシア・スペイン・ポルトガルなど各国宮廷から注文が殺到したそうです。 マリー・アントワネットの選んだ色は「王妃の色」として大流行しましたし、アントワネットのグレーシュなブロンズの髪の色のかつらから身につける宝石類、そして彼女が好きなお菓子までがヨーロッパ中で貴族やブルジョワに好まれたのです。 まさに当時のファッションリーダーであったわけですね。 フランスの今に続くファッションイメージはこの頃に育まれたものといえるでしょう。 そうしますと決して高い買い物ではなかったようにも思えます。 田舎風ドレスのマリー・アントワネット アントワネットはロココファッションの女王というイメージが強いのですが、それだけではないようです。 むしろロココの舞台である宮廷から遠ざかり、自分にとっての大事なものを追い求めた姿はロココの破壊者ともいえるように思います。 誰よりも早く華美なドレスを脱ぎ、パニエを外し、田舎娘風の簡素なスリップドレスをつくらせます。 1783年、突然ロココのドレスは終焉を迎え、ネオ・ギリシャ・ローマ風のシンプルなスリップドレルがとってかわりパニエは見られなくなりなります。 この流れはアントワネットの田舎娘風スリップドレスの影響も無関係ではなかったでしょうし、ジャン・ジャック・ルソーの説いたシンプルな生き方、財政的についていけなくなった貴族などの要因が見られます。 しかし、皮肉なことにこの極端で急激なモードの変換によりリヨンを中心とした繊維産業に大打撃を与えフランスの経済破綻を早め、1788年とうとう国は手形の交換を停止することになり、翌年のバスティーユ襲撃に繋がります。...
ロココの女王 マリー・アントワネット
アントワネットは湯水のごとくドレスに国費を使って国を傾けたといわれていますが、本当はどうだったのでしょう。 半世紀前の1725年から王妃の衣装代は年間12万ルーブルと予算が組まれていました。 シーズンごとに正装用、礼装用、ドレスを各3枚、年間にすると各12枚が新調される約束で、最低でも36着は規則によって与えられます。 これとは別に王妃にはお手元金という300〜400ルーヴルのポケットマネーの予算もありました。 しかし、実際の王妃のお買い物は年間170着のドレス、25万ルーブルの腕輪や50万ルーブルの耳飾りなども求めています。 日本からも漆器の化粧道具箱や宝石箱などを注文して作らせています。 2年程前にそれらのアントワネットコレクションの数々を京都の国立博物館で観てまいりました。 他の海外の漆器のコレクションに比べ、女性的なセンスの良さには驚かされました。 展示内容に若干の違いがありますが、東京ではサントリー美術館でも展示がされたのでご覧になられたかとも多いと思います。 さて、大きく予算を超えていますが王室の費やす金額は果たして財政を破綻させるほどのものなのでしょうか。 王室の費用というのは国庫の10%に満たない額です。 国庫の10%、大きいですがそれだけでは国が破綻するとは思えません。 マリア・テレジアはマリー・アントワネットへファッションへの逃避を慎むように手紙を送っていました。 マリー・アントワネットはローズ・ベルタンに「パンドラ」という木と陶器のお人形をつくらせます。 そしてそれにベルタンのつくる最新のモードのドレスを着せ、絹の靴下からアクセサリー、宝石、最新のヘアースタイルのカツラ、帽子や孔雀の羽などの全てを身につけさせ母マリア・テレジアと姉妹たちへの贈ります。 これが非常に人気をよび、等身大に近いものがつくられるようになります。 これを各国王室・宮廷に送り、さらなる流行を作りだし、注文を受けたのでした。 フランスの殖産産業としてのファッション戦略はすでにありましたが、これほど明確なものはかつて無かったように思います。 ロシア・スペイン・ポルトガルなど各国宮廷から注文が殺到したそうです。 マリー・アントワネットの選んだ色は「王妃の色」として大流行しましたし、アントワネットのグレーシュなブロンズの髪の色のかつらから身につける宝石類、そして彼女が好きなお菓子までがヨーロッパ中で貴族やブルジョワに好まれたのです。 まさに当時のファッションリーダーであったわけですね。 フランスの今に続くファッションイメージはこの頃に育まれたものといえるでしょう。 そうしますと決して高い買い物ではなかったようにも思えます。 田舎風ドレスのマリー・アントワネット アントワネットはロココファッションの女王というイメージが強いのですが、それだけではないようです。 むしろロココの舞台である宮廷から遠ざかり、自分にとっての大事なものを追い求めた姿はロココの破壊者ともいえるように思います。 誰よりも早く華美なドレスを脱ぎ、パニエを外し、田舎娘風の簡素なスリップドレスをつくらせます。 1783年、突然ロココのドレスは終焉を迎え、ネオ・ギリシャ・ローマ風のシンプルなスリップドレルがとってかわりパニエは見られなくなりなります。 この流れはアントワネットの田舎娘風スリップドレスの影響も無関係ではなかったでしょうし、ジャン・ジャック・ルソーの説いたシンプルな生き方、財政的についていけなくなった貴族などの要因が見られます。 しかし、皮肉なことにこの極端で急激なモードの変換によりリヨンを中心とした繊維産業に大打撃を与えフランスの経済破綻を早め、1788年とうとう国は手形の交換を停止することになり、翌年のバスティーユ襲撃に繋がります。...