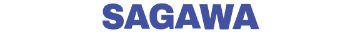アントワネットは湯水のごとくドレスに国費を使って国を傾けたといわれていますが、本当はどうだったのでしょう。
半世紀前の1725年から王妃の衣装代は年間12万ルーブルと予算が組まれていました。
シーズンごとに正装用、礼装用、ドレスを各3枚、年間にすると各12枚が新調される約束で、最低でも36着は規則によって与えられます。
これとは別に王妃にはお手元金という300〜400ルーヴルのポケットマネーの予算もありました。
しかし、実際の王妃のお買い物は年間170着のドレス、25万ルーブルの腕輪や50万ルーブルの耳飾りなども求めています。
日本からも漆器の化粧道具箱や宝石箱などを注文して作らせています。
2年程前にそれらのアントワネットコレクションの数々を京都の国立博物館で観てまいりました。
他の海外の漆器のコレクションに比べ、女性的なセンスの良さには驚かされました。
展示内容に若干の違いがありますが、東京ではサントリー美術館でも展示がされたのでご覧になられたかとも多いと思います。
さて、大きく予算を超えていますが王室の費やす金額は果たして財政を破綻させるほどのものなのでしょうか。
王室の費用というのは国庫の10%に満たない額です。
国庫の10%、大きいですがそれだけでは国が破綻するとは思えません。
マリア・テレジアはマリー・アントワネットへファッションへの逃避を慎むように手紙を送っていました。
マリー・アントワネットはローズ・ベルタンに「パンドラ」という木と陶器のお人形をつくらせます。
そしてそれにベルタンのつくる最新のモードのドレスを着せ、絹の靴下からアクセサリー、宝石、最新のヘアースタイルのカツラ、帽子や孔雀の羽などの全てを身につけさせ母マリア・テレジアと姉妹たちへの贈ります。
これが非常に人気をよび、等身大に近いものがつくられるようになります。
これを各国王室・宮廷に送り、さらなる流行を作りだし、注文を受けたのでした。 フランスの殖産産業としてのファッション戦略はすでにありましたが、これほど明確なものはかつて無かったように思います。
ロシア・スペイン・ポルトガルなど各国宮廷から注文が殺到したそうです。
マリー・アントワネットの選んだ色は「王妃の色」として大流行しましたし、アントワネットのグレーシュなブロンズの髪の色のかつらから身につける宝石類、そして彼女が好きなお菓子までがヨーロッパ中で貴族やブルジョワに好まれたのです。
まさに当時のファッションリーダーであったわけですね。
フランスの今に続くファッションイメージはこの頃に育まれたものといえるでしょう。

田舎風ドレスのマリー・アントワネット アントワネットはロココファッションの女王というイメージが強いのですが、それだけではないようです。
むしろロココの舞台である宮廷から遠ざかり、自分にとっての大事なものを追い求めた姿はロココの破壊者ともいえるように思います。
誰よりも早く華美なドレスを脱ぎ、パニエを外し、田舎娘風の簡素なスリップドレスをつくらせます。
1783年、突然ロココのドレスは終焉を迎え、ネオ・ギリシャ・ローマ風のシンプルなスリップドレルがとってかわりパニエは見られなくなりなります。
この流れはアントワネットの田舎娘風スリップドレスの影響も無関係ではなかったでしょうし、ジャン・ジャック・ルソーの説いたシンプルな生き方、財政的についていけなくなった貴族などの要因が見られます。
しかし、皮肉なことにこの極端で急激なモードの変換によりリヨンを中心とした繊維産業に大打撃を与えフランスの経済破綻を早め、1788年とうとう国は手形の交換を停止することになり、翌年のバスティーユ襲撃に繋がります。
次からはそんな悲劇の王妃の生涯を追ってみたいと思います。
アンティークエタラージュでは現代のお洋服でも使えるきちんとした本物のアンティークジュエリーであることにこだわりを持ったセレクションと、可愛らしいモノからミュージアムピースまで、幅広いコレクションがあなたをお待ちしています。
天使のモチーフの数の多さも特徴の一つです。
アンティークジュエリーを愛するみなさまのお越しをお待ちしております。
移転を機に、お客さまがお使いにならなくなったアンティークジュエリーのお預かりも始めました。
まずは「お預かり」のご案内 をご覧ください。
『エタラージュがあなたの街へ』 詳しくはこちらをご覧ください。
『あなたのお店でアンティークジュエリーを扱ってみませんか』 詳しくはこちらをご覧ください。