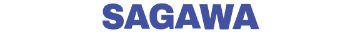身を装う為にあるジュエリーとファッションは当然、密接な影響があります。
そこでファッションにもふれておこうと思います。
宮廷ファッションが花開くのはロココの頃ですが、ロココファッション自体はパニエ(※1)やトゥルニュール(※2)のように腰から横にスカートを大きくふくらませたスタイルで、ドレススタイル自体に変化はあまりなく、ひだ飾りや様々な宝石、ローブやかぶり物で変化をつけたもので、今日のように定期的にモードが変わるのは19世紀中期頃といえます。
中世よりファッションの中心的役割を果たしてきたフランスですが、14世紀に仕立て屋の同業組合が結成され特権を持ちファッション界を独占していました。
この組合員は男性のみで行われ、彼らが作る堅苦しく変化に乏しい服は当然女性からは不満を持たれモグリの女性裁縫師が現れます。
彼女たちは組合から報復を受けながらも後のルイ14世妃となるマダム・ド・マントノン(※3)ら有力な宮廷婦人の後ろ盾でルイ14世から勅許をうけ、服を作る権利を勝ち取ります。
1675年、こうしてできたのが女性裁縫師組合です。
しかし、この組合も自由に服が作れた訳ではなく、表立っては8歳以下の男の子の服と女性の下着の製作というものでした。
当然、裏では注文を受け作っていたでしょうが、100年後大きく権利を獲得します。
1776年、小間物屋が中心となり婦人服モード商組合が結成され女性も加入が認められます。
女性なら誰でも入れた訳ではないでしょうけどね。
そしてモード商ともいえる婦人服の製作責任の立場を作りだし、それ迄の仕立て屋や裁縫師と連携し、彼らに作らせた服に様々な装飾を施しファッションを作るデレクター的な役割を果たしだします。
装飾だけで巨額な利益を出す専門家が現れ装飾は一層過剰になっていったともいえます。
この組合員は18世紀末にはアクセサリーの製作も初めています。
それ迄の単一の職人仕事には見られなかった何種類もの技法を使ったジュエリーが作られるようになったのです。
又、1770年から1790年にかけて15種類の定期刊行のファッション誌が発刊されます。
中には彩色されたファッション画が描かれ新たなファッション戦略の始まりともいえます。
ロココのファッションが花開くにはこうした背景があったのです。
さて、ロココのジュエリーですが、マリー・アントワネットの肖像画やファッションプレートをご覧になられるとイメージがつかめます。
マリー・アントワネットは別稿で書こうと思っていますがヴェルサイユの頃とトリアノンの頃とで大きくファッションが違います。
まだ、ブローチの時代ではなく、服に直接宝石やパールを縫い付けています。
ピアスやネックレスはありますが、装飾の為のかぶり物が特徴的ですね。
まだ、アフリカのダイヤモンド鉱山もアメリカの金鉱も発見されていないので宝飾品の価値は非常に高いものでした。
特別な階級の人の為にあったものです。
庶民には触るどころか見ることもかなわなかったものです。
ジュエリーが一般的になるにはまだ時間が必要ですが、この時代の大きなキーワードであるエレガンスという感覚は今に近づく程薄くなってゆくように思えます。
あなたもエタラージュでエレガンスはいかがでしょう。
註>