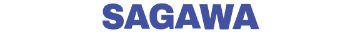18世紀からファッションの影響力は男性はイギリスの紳士服、女性はフランスの婦人服という傾向がありましたが、19世紀に入ると新興富裕層の台頭や産業革命による生産体制の変化によりこの傾向は一層明確なものとなりました。
流行のサイクルは社会が複雑になってゆく中、様々な要因により短期間の流行となってゆきました。
19世紀初頭ジョージ・ブランメルが提唱するダンディズムによりそれを指標としたメンズファッションが19世紀末までに確立され、それは現代へ受け継がれているものでもあります。
1820〜1830年代
絵画や文学・演劇のロマン主義を受け、ファッションにもロマン主義の影響が見られるようになります。
幻想的・理想的・異国趣味という指向をもつロマン主義では女性はか弱くはかなく男性に従順なものとされ、健康的な快活さは下品とされ、青白い顔が好まれました。
クラッシクバレエのチュチュもこの頃に作られたものです。
その影響か、スカート丈はそれまでより短くなります。
18世紀以来高くなっていたウエストラインが元の低い位置に戻り、ウエストを細くみせるためコルセットが復活、スカートがふくらみ始めます。
この時代の特徴的なジゴ袖といわれる肩から袖口まで大きくふくらんだ袖は1830〜1835年にかけて極端に大きくなります。
ネックラインは下がり、夜のドレス特に胸元が大きく空いたものとなり、昼間は開いたネックラインをケープやショールを使って控えめに見せた。
この時期に始まった縦長にカールさせ両脇にたらした髪型は19世紀半ばまで続きました。
帽子は大きなモノにリボン・造化・宝石で飾られたものが流行りました。
1840~1850年代
シルエットに変わりはありませんが極端なパターンは廃れ、より女性性が強調されウエストラインはさらに下がり、スカートはペティコートを何枚も重ねますます膨らみます。
50年代のスカートにはフリルの段飾りが付きます。
30年代短かったスカートは40年代は地面に届く長さになります。
レースやフリルがたれる襟、それまで極端に膨らんだジゴ袖は襟と一体化した袖や袖口だけ膨らんだものへ変わります。
帽子はボンネットなどの小さなものになります。
上流の婦人に求められるものは控えめで夫に献身的であり、夫に守られた弱い存在であり、労働は悪徳というものでした。
クリノリン
「クリノリン」とは馬の尻尾の毛を指す「クラン(crin)」と、麻布を指す「ラン(lin)」を合成してできた言葉。もとはスカートを膨らませるためにペチコート(スカートの中に入れる釣り鐘型フレーム)の繊維素材として使われた馬の毛入りの木綿(もしくは麻)だったが、そのままスカートのスタイル名として使われた。
1,830年頃に作られた、馬の毛を織り込んで硬くしたペチコート用の木綿、または麻。
それまでスカートを膨らませるために何枚も重ね履きする必要のあったペチコートに変わってドーム型のシルエットが容易に得られるようになった。1850年代後半にスカートを膨らませるために発明された鯨ひげや針金を輪状にして重ねた骨組みの下着である(後に材質は変化)。1860年代に入るとクリノリンはその形を変化させ、さまざまなバリエーションが生まれた。ヴィクトリア朝時代のイギリス女性の間で爆発的に広まりこのクリノリンによってスカートの裾は大きく広がれば広がるほど良いという風潮になった。クリノリンが巨大化した理由の一つが1856年、皇太子(ナポレオン4世)を身ごもっていたフランスのウジェニー皇后である。彼女は姿態の不恰好を隠すためにクリノリンを極端に拡大して使っていた。それが新しいモードとしてサロンに受け入れられ、1850年代末には、クリノリンの大きさは最大値に達した。この巨大化は1860年代まで続いた。
しかし動くたびにクリノリンが引っかかって転倒したり、暖炉などの火がスカートに引火して火傷をしたりという事故が多発することになった。一説に年間3,000人の人間がクリノリンによる事故で死亡し、20,000人の人間が事故にあったといわれる。
バッスルスタイル
1,864年には後ろだけ膨らみを残したり、単純な輪ではなくてスカートを自然な形に成形するような形状のものも使われるようになりました。